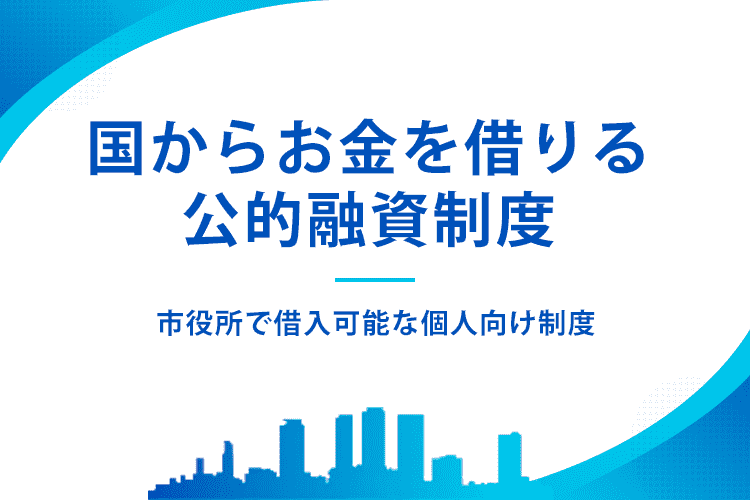
![]()
どこからもお金を借りられずに困っている人は、国から借りられる12種類の公的融資制度を利用できる可能性があります。
国の公的融資は個人と事業で分けると12種類あり、自治体にも目を向けるとさらに細かい制度に分類されています。
このページでは個人が利用可能な公的融資の申請条件や申し込み手順を解説。
公的融資を受ける時にどの方法を利用すべきか迷う方に、一覧表を用いて条件別で紹介していきます。
早速、国からお金を借りたいときに使える12種類の公的融資制度を見ていきましょう。
公的融資制度とは、低所得世帯や高齢者世帯、障がい者世帯をはじめ、生活が困窮した世帯を保護する目的で、国や自治体が融資を行う制度です。
公的融資制度は無利子または低金利で、返済時の負担を大きく軽減できるのがメリット。
公的融資は個人にのみ使える制度と、法人(企業)が使える事業者対象の制度があります。
それぞれ利用できる対象者や限度額が違うので、自分が借りられるのはどの制度かチェックしておきましょう。
| 制度 | 借りられる人 | 貸付の種類 | 金利 | 限度額 | 連帯保証人 | 融資スピード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活福祉資金貸付制度 | 低所得者世帯 障害者世帯 高齢者世帯 | 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)※ 福祉資金(福祉費、緊急小口資金※) 教育支援資金(教育支援費、修学支度費) 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金) ※生活支援資金、緊急小口資金は自立相談支援事業の利用が貸付条件となる | 連帯保証人を立てるならば無利子 連帯保証人を立てないならば年1.5% ※緊急小口資金、教育支援資金は無利子 | 総合福祉資金:~60万円 福祉資金:580万円 緊急小口資金:10万円 教育支援資金:50万円 不動産担保型生活資金:土地の評価額70%以内、月30万円以内、生活扶助額の1.5倍以内のうちいずれか | 必要 ※無しの場合は金利の負担があります | 1ヶ月 ※緊急小口資金に限り5日 |
| 求職者支援資金融資制度 | 職業訓練受講給付金の支給決定を受けている人 ハローワークで求職者支援資金融資確認書の交付を受けた人 | - | 年3.0% | 月額5万円または10万円✕受講予定訓練月数 | 不要 ※労働金庫の指定する信用保証機関の利用が条件 | 1ヶ月 |
| 勤労者融資制度 | ・融資制度を提供している自治体に住所があり、中小企業に勤務している人 ・または勤務先の業績悪化や倒産により収入減少、離職した人 | 生活資金 教育資金 住宅資金 ※各自治体による | 年1.2~3.0% ※各自治体による | 生活資金:100万円 教育資金:300万円 住宅資金:300万円 ※各自治体による | 不要 | 1週間 |
| 東京都中小企業従業員生活資金融資制度 | ・東京都に在住もしくは在勤している中小企業従業員 ・都内で家内労働に従事している人 | 個人融資(さわやか) 子育て・介護支援融資(すくすく・ささえ) 家内労働者生活資金融資 | 個人融資・家内労働者生活資金融資:1.8% 子育て・介護支援融資:1.5% | 70~130万円 | 原則不要 | 1週間 |
| 教育一般貸付 | 低所得世帯で入学もしくは在学する子どもがいる保護者 | - | 年1.80% 一部条件に該当する世帯は-0.4%適用 | 350万円(子ども1人あたり) 自宅外通勤、5年以上大学、大学院、海外留学の場合:450万円 | 必要 ※なしの場合、教育資金融資保証基金の利用が必要 | 3週間 |
| 看護師等修学資金 | 看護師養成施設に在学中で、将来看護業務に従事する意思がある人 | - | 無利子 | 月額2~10万円前後 ※各自治体による | 必要 | 申し込んだ直近の振込時期 |
| 日本学生支援機構奨学金 | 大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程) および大学院で学ぶ人 | 第一種(無利子) 第二種(有利子) 入学時特別増額 海外留学支援制度 | 制度により異なる | 制度により異なる | 必要 | 申し込んだ直近の振込時期 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | ・20歳未満の子どもを育てている母子家庭もしくは父子家庭の児童 ・父母のいない児童 ・寡婦が扶養する子ども | 事業開始資金 事業継続資金 修学資金 技能習得資金 修業資金 就職支度資金 医療介護資金 生活資金 住宅資金 転宅資金 就学支度資金 結婚資金 | 保証人ありの場合は無利子 保証人なしの場合: | 制度により金額差あり | 必要 ※なしの場合、利息の負担あり | 1~3ヶ月 |
| 女性福祉資金 | 東京都に6ヶ月以上在住で配偶者のいない女性 | 事業開始資金 事業継続資金 技能習得資金 就職支度資金 医療介護資金 生活資金 住宅資金 転宅資金 結婚資金 修学資金 就学支度資金 | 年1% ※保証人ありの場合は無利子となります | 制度により金額差あり | 必要 ※なしの場合、利息の負担あり | 1ヶ月 |
| 日本政策金融公庫 | 事業者 | 国民生活事業 中小企業事業 農林水産事業 | 制度により異なる | 制度により金額差あり ※平均700万円 | 制度により異なる | 2週間 |
公的融資の最大のメリットは、とにかく低金利である点です。
あくまでも生活に困っている人向けの制度なため、利息によって圧迫されることのないよう設定されています。
中には無利子で借りられるものもあり、カードローンの審査に通らないアルバイトや派遣でも借りられるのが特徴。
借り入れの際は、以下のどちらかを選ぶ場面が多いです。
- 利子あり、連帯保証人なし
- 利子なし、連帯保証人が必要
借り入れが周囲にバレたくない人や、周りに相談できない人は連帯保証人を付けなくても利用可能。
利息があるといっても1~3%程なので、保証人を付けるくらいなら利息を払って済ませたいと考える人も少なくありません。
一方で身近に連帯保証人がいる人は、保証人をつけて無利子で利用するのがベスト。
貸付条件は制度によって異なるため、ひとつずつ詳しく紹介していきます。
年金担保貸付は令和4年3月末で制度が終了している
現在、年金担保貸付融資は新規申込・貸付を終了しています。
年金を担保に借り入れする方法はないため、他の貸付制度を利用してください。
政府では、年金担保貸付制度の代わりに生活福祉資金貸付制度の利用を推奨しています。
年金担保貸付制度以外に年金を担保とした貸し付けは許可されていないので、「年金を担保に借りられる」と宣伝している業者は高い確率で違法業者。
トラブルに巻き込まれる可能性が高いので、利用は避けてください。
「生活福祉資金貸付制度」は幅広い目的に適しているため個人で借入に利用できる
公的融資制度の中で、いろいろな目的に対応しているのが「生活福祉資金貸付制度」です。
生活福祉資金貸付制度は厚生労働省の取り扱いで、市役所(社会福祉協議会)が窓口となって以下のようなあらゆる用途で借りられます。
| 資金の種類 | 資金詳細 |
|---|---|
| 総合支援資金 | 生活支援資金 住宅入居費 一時生活再建費 |
| 福祉資金 | 福祉費 緊急小口資金 |
| 教育支援資金 | 教育支援費 就学支度費 |
| 不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 |
生活福祉資金貸付制度で借りられる対象となるのは、以下の世帯に属する人です。
障害者世帯:身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた世帯
高齢者世帯:65歳以上の高齢者がいる世帯
※参照:厚生労働省|生活福祉資金制度について
低所得者世帯の基準となるのは、市町村民税の住民税非課税世帯に該当しているかどうか。
つまり現在、住民税を支払っていない世帯は低所得者世帯として貸付対象となる可能性が高いです。
住民税非課税世帯とは?
世帯年収が一定の金額を下回ると、世帯全体で住民税の支払いが免除されます。
市町村や世帯状況によって年収の目安は変わるものの、目安となる所得は以下のとおり。
・独身男性の場合:給与収入100万円以下
・会社員と専業主婦、子ども1人の場合:205万円以下
・会社員と専業主婦、子ども2人の場合:255万円以下
上記の所得を下回った世帯に関しては、住民税非課税世帯として生活福祉資金貸付の対象となるケースが多いでしょう。
なお高齢者世帯と障害者世帯は、それぞれ高齢者と障碍者に該当する人が世帯内に1人でもいれば対象となります。
最短・無利子で融資を受けるなら緊急小口資金
生活福祉資金の中でも特別に、緊急的な貸付を行っているのが緊急小口資金です。
公的融資は低金利で利用できて便利ですが、融資までに最低でも1週間程度、長くて1ヶ月以上かかるのがデメリット。
ただし「事故や入院で急にお金が必要になった」「職場の事情で退職せざるを得なくなった」といった、一時的に必要な人や緊急の理由がある人は「緊急小口資金」を利用できます。
現在緊急小口資金は、令和6年能登半島地震で被害を受けた世帯向けの緊急的な貸付制度となっています。
通常10万円しか借りられない制度ですが、条件に当てはまる世帯は貸付金額を20万円まで増額。
保証人不要、無利子で借りられるので、なるべく早く生活費を補填したい人は緊急小口資金を利用しましょう。
現在、緊急小口資金を利用できる対象者は以下のとおりです。
- 石川県、新潟県、富山県、福井県に住んでいる
- 世帯員の中に死亡者がいる
- 世帯員に要介護者がいる
- 世帯員が4人以上いる
- 上記のほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認めている
緊急小口資金は基本的に、緊急性が高い生活費の貸し付けが目的です。
その他の理由では貸し付けが認められない場合が多いので、違う公的融資制度の利用を検討してください。
また、上記の緊急小口資金と、失業を理由に借り入れできる総合支援資金は、生活福祉資金の特例貸付と呼ばれています。
特例貸付を利用してもなお生活が困窮する場合は、セーフティネットとして用意されている給付金の利用も検討してください。
公的融資で休職中の人が借りられる方法や制度
現在失業中で仕事を探している人は、国の「求職者支援資金融資制度」を利用して借りられます。
求職者支援資金融資制度で借りられる金額の上限は、月額5万円(同居配偶者がいる場合は月10万円)です。
公的融資とはいえ貸付は各地域のろうきん(労働金庫)が行い、窓口はハローワークとなっています。
申込条件は、職業訓練受講給付金の決定を受けており、ハローワークにおいて融資制度の要件確認書を交付してもらった人のみです。
職業訓練受講給付金は、月額10万円+通所手当が給付される制度。
上記の給付のみでは生活費が不足する場合にのみ、求職者支援資金融資制度が利用できます。
簡単に言うと、毎月10万円の収入(給付金)のみでは生活できない人向けの融資制度です。
預貯金がなく、仕事をしていない単身世帯の場合、家賃や生活費を10万円でまかなうのは難しいでしょう。
以上のように、やむを得ない事情で生活が困窮する可能性がある人向けに用意されています。
仕事を探していれば誰でも借りられるわけではないので注意しましょう。
収入が減ったり離職した時に借りられる勤労者生活支援特別融資制度
同じく離職した時や収入が減少した時には「勤労者生活支援特別融資制度(勤労者福祉資金融資制度)」が利用できます。
自治体によって呼び方は異なっており、自治体とろうきんが提携している自治体ローンです。
勤労者融資制度の貸付対象者も自治体によって異なります。
一例として、全国各地方ろうきんの申込対象者を比較してみましょう。
| 地方ろうきん | 申込対象者 |
|---|---|
| 九州ろうきん | ろうきんローンの利用者で、以下の条件に該当する人 【収入が減少した人】 【離職した人】 |
| 中央ろうきん(茨城県勤労者緊急生活支援) | ・茨城県に居住または勤務している一般労働者 ・茨城県内に1年以上居住または勤務している ・現在の勤務先に勤続1年以上、前年度年収150万円以上 ・中央労働金庫の基準ならびに保証期間の保証基準を満たしている |
※参照:勤労者生活支援特別融資制度|九州ろうきん
勤労者向け融資制度のご案内|茨城県
九州ろうきんでは外的な理由で収入が減少した人を原則対象としていますが、茨城県(中央ろうきん)では収入の増減に関係なく、労働者であれば利用可能です。
多くは収入が減少した人、または離職者向けの制度なので、勤務先の事情で収入が減ってしまった人は自治体に相談しましょう。
勤労者生活支援特別融資制度も金利が低く設定されており、年1.5~3.0%前後で借り入れできるのが特徴です。
東京の中小企業で勤めている人が利用可能な「東京都中小企業従業員生活資金融資」
ほかにも東京都に住んでいれば中央ろうきんで「東京都中小企業従業員生活資金融資」を利用できます。
以前は「中小企業従業員生活資金融資制度」という名称で提供されていた融資制度ですが、サービス内容は据え置きで「東京都中小企業従業員生活資金融資」に名称を改めました。
東京都中小企業従業員生活資金融資の内容は下記の3種類。
- 個人融資(さわやか)
- 子育て・介護支援融資(すくすく・ささえ)
- 家内労働者生活資金融資
いずれも都内に住んでいる、もしくは都内で働いている人が対象で、1.5~1.8%で借りられます。
東京都中小企業従業員生活資金融資の大きな特徴は、家内労働者向けの融資制度を用意していること。
家内労働者とは、自宅を作業場として製造・加工といった仕事に従事し、生計を立てている人を指します。
いわゆる内職で生計を立てている人も家内労働者に分類される場合が多いです。
働きに出ていない主婦が内職で生計を立てている場合も、貸付対象として認められる場合があります。
教育資金のために利用できる2つの公的融資制度
子どもが入学するときの入学金や修学資金を借りたい家庭は、国の教育資金貸付制度を利用できます。
教育資金に係る公的融資は大きく分けて2つ。
- 教育一般貸付
- 教育支援資金
教育の公的融資制度は義務教育後の高校(高専)、大学(短大・専門学校)の学費が対象です。
文科省が出している推移を見ると、大学の授業料は年々上昇傾向にあります。それに合わせて教育資金を借入する世帯も増加しています。
親の年収が基準より高くても借りられる「教育一般貸付」
日本政策金融公庫が取り扱っている「教育一般貸付」は、借り入れできる年収の上限が幅広く設定されており、より多くの人が借りられる方法です。
教育支援資金や奨学金は、親の年収をもとに審査が行われるため、親の年収が高いと審査に通らない家庭も少なくありません。
一方で「教育一般貸付」は国の制度である側面から、扶養する子どもの人数が多ければ、親の年収が国の平均年収(467万円)を上回っていても借りられます。
※参考:平均給与|国税庁
教育一般貸付を利用できる世帯年収の上限額は以下のとおりです。
| 子どもの数 | 世帯年収上限額(所得上限) |
|---|---|
| 1人 | 790万円(600万円) |
| 2人 | 890万円(690万円) |
| 3人 | 990万円(790万円) |
| 4人 | 1,090万円(890万円) |
| 5人 | 1,190万円(990万円) |
教育一般貸付は、入学した時に借りられる日本学生支援機構の奨学金とは違い、入学時期に限らず、1年中いつでも借入可能で、年利1.66%とかなりの低金利です。
とはいえ奨学金のように学費を全額借りられるわけではなく、借り入れの上限は350万円までと決められています。
奨学金と併用できるため、入学金のみの支払いや、一時的に教育費用が必要なときに利用するといいでしょう。
低所得世帯が借りられる教育支援資金
教育支援資金は生活福祉資金のひとつで、低所得者世帯が対象の融資制度です。
先ほど紹介した教育一般貸付と異なり、教育支援資金を利用できる収入上限は以下のとおりです。
| 子どもの数 | 世帯年収上限額 |
|---|---|
| 2人 | 27万2,000円 |
| 3人 | 33万5,000円 |
| 4人 | 38万5,000円 |
| 5人 | 42万5,000円 |
参照:教育支援資金のご案内
無利子で教育資金を借りられるため、生活福祉資金貸付制度の中でも20代~30代の申込者が多い特徴もあります。
参照:生活福祉資金ユーザー(借受人)による事業評価に関する調査研究事業報告書
入学費用は50万円まで、修学費用は大学なら月額6.5万円までが限度額です。
教育支援資金は各自治体の市役所ではなく、社会福祉協議会に連絡をしましょう。
看護師を目指している学生は看護師等修学資金を利用できる
看護師や看護職員を目指している学生は、自治体に申請すると「看護師等修学資金」を利用できます。
自治体によって金額は異なっており、月額2~5万円程度の借り入れが可能です。
基本的には返済が必要なものの、市内の医療機関で継続して働くことで返済が免除されるケースもあります。
参照:佐賀県看護師等修学資金貸与条例
また、同じく佐賀県伊万里市では、以下の資格免許を取得し、市内に居住・就職した人が連携協定した金融機関の奨学金を返済する場合、利子相当額を補助してくれる制度も。
- 看護師
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 保育士
実質無利子で奨学金を借りられる制度なので、居住する地域にある様々な教育関連の融資・給付サービスを事前に調べておきましょう。
母子・父子家庭が国から公的融資で借りられる融資の種類を紹介
現在、母子家庭(父子家庭)にある家庭は「母子父子寡婦福祉資金貸付金」で借りられます。
母子父子寡婦福祉資金貸付金で借りられる融資の種類は以下の12種類。
- 事業開始資金
- 事業継続資金
- 修学資金
- 技能習得資金
- 修業資金
- 就職支度資金
- 医療介護資金
- 生活資金
- 住宅資金
- 転宅資金
- 就学支度資金
- 結婚資金
上記のうち、修学資金や修業資金、就職支度資金、就学支度資金は父母のいない子どもも利用可能。
母子・父子家庭だけでなく、様々な事情で親がいない子どもも利用できる制度なのはあまり知られていません。
金銭的な理由で就学を諦めなければならない人は、まず母子父子寡婦福祉資金貸付金の利用を検討しましょう。
いずれも保証人がいる場合は無利子、保証人がない場合は年利1.0%で借りられます。
東京都に住んでいる女性は女性福祉資金も利用できる
国が取り扱う「母子父子寡婦福祉資金貸付金」のほかに、自治体によっては似ている制度があります。
東京都に住んでいる女性の場合、「女性福祉資金」と呼ばれる制度を利用可能です。
女性福祉資金を受けられる条件
- 都内の市町村に6ヶ月以上住んでいる
- 配偶者のいない女性
母子父子寡婦福祉資金と同じように11種類の資金に分かれており、本人の生活費や就業費にくわえ、子どもの修学費用など幅広い借り入れができます。
利子は無利子で、保証人がいない場合は年利1%の低金利で借りられます。
借入条件は、同じ東京都内でも区や市によって違います。
| 自治体 | 借入条件 |
|---|---|
| 東大和市 | 都内に6ヶ月以上在住し、配偶者がいない、もしくは配偶者がいても扶養を受けられない女性で以下の条件に該当する人 ・親、子ども、兄弟を扶養している ・上記を扶養していない年間所得203万6,000円以下の人で、かつて母子家庭で子どもを扶養していた、または婚姻歴がある40歳以上の人 |
| 板橋区 | 配偶者がいない女性で、以下全ての要件を満たす人 ・25歳以上の人、もしくは25歳未満で直系の親族または兄弟姉妹を扶養している ・他から同種の資金を借り受けることが困難 |
居住する地域の貸付条件を確認した上で、対象となる人は申し込むのをおすすめします。
公的融資を受給するまでに借り入れたいなら臨時特例つなぎ資金貸付制度
すでに公的給付や公的融資を受けることが決まっていて、かつ支給や融資を受けるまでの生活が苦しい人は、臨時特例つなぎ資金貸付制度を利用できます。
臨時特例つなぎ資金貸付制度の条件
- 住居がない離職者
- 公的給付・公的融資の申請が受理されており、給付開始までの生活に困窮している
- 本人の銀行口座を保持している
公的給付は生活保護だけでなく、失業保険や職業訓練受給給付金なども対象となります。
臨時特例つなぎ資金貸付制度は、給付や融資を受けるまでのつなぎ融資のため、限度額は10万円まで。
すでに公的給付や融資を受けられる権利があるので、連帯保証人がいなくても無利子で借りられる制度です。
あくまで臨時の融資なので、公的給付や融資を受けた1ヶ月以内に貸付金全額を返済する必要があります。
注意すべきは公的給付や融資の申請が通らなくても、貸付金を全額返済する必要がある点です。
臨時特例つなぎ資金貸付で借りられる時点で却下される確率は低いですが、虚偽の申請により却下されるケースも稀にあります。
臨時特例つなぎ資金貸付制度は原則として一括返済となるため、資金の扱いに注意しましょう。
ここまでは個人向けの公的融資制度をまとめて紹介しました。
ここからは個人の融資ではなく、会社として借りたい人へ、事業者向けの制度を紹介します。
小規模事業者が国からお金を借りるなら公的融資制度の小口資金融資がおすすめ
事業者の場合、日本政策金融公庫の融資制度を利用するのが最も便利です。
日本政策金融公庫は大きく分けて次のような3つの事業に分かれています。
- 国民生活事業
- 農林水産事業
- 中小企業事業
国民生活事業は前述した教育一般貸付を含む、小規模事業者やスタートアップ企業に対して融資を行う事業です。
小規模事業者向けの融資で最も金利が低いのが、商工会議所で利用できる「マル経融資」。
無担保・保証人不要で借りられる制度なので、20人以下の小規模事業者はぜひ利用を検討しましょう。
日本政策金融公庫では小口資金融資にくわえて、新規開業資金も借りられます。
担保の有無によって金利は変わり、およそ年利1~2%の間で借入が可能です。
自営業者(個人事業主・フリーランス)がお金を借りる制度は?
日本政策金融公庫に申請を行うと、個人事業主がお金を借りることも可能です。
ただし、法人が日本政策金融公庫を利用する場合と提出する書類が異なります。
はじめて借り入れする場合は創業計画書も提出しなければならないため、融資制度に詳しくない人は準備に戸惑う場合もあります。
分からない内容がある人は、日本政策金融公庫の事業資金相談ダイヤルに電話してください。
必要書類や個人事業主が利用できる融資制度について、詳しく説明してもらえます。
一方、緊急で借りなければいけない場面や、一時的な資金繰りに困っている方であれば、個人向けの緊急小口資金を紹介されることもあります。
国の融資でお金を借りるデメリット!国から即日借りるのは難しい
民間より低金利で借りられて便利な公的融資ですが、デメリットもあります。
公的融資のデメリット
- 公的融資は即日借りられない
- 手続きが面倒(窓口へ足を運ぶ必要がある)
公的融資は受けられるかどうか慎重に審査が行われるため、即日の融資に対応していません。
最も早く借りられる緊急小口資金であっても最短5日はかかります。
中には融資を受けるまでに1ヶ月以上かかる制度もあるので、今日お金が必要と考えている人には向いていません。
また書類を用意する必要があったり、窓口へ足を運んだりと手続きが面倒なのも公的融資のデメリット。
借り入れには、役所やろうきん・銀行へ何度も足を運ぶ必要があります。
最寄りに役所や金融機関がない人にとっては、何度も足を運ばなければいけないのは大変です。
「今すぐお金が必要」
「なるべく手間なく借りたい」
「役所が近くにない」
このような状況の人は、公的融資を利用する前に消費者金融を選ぶのがベストでしょう。
金利が高くて不安な人も、消費者金融の無利息サービスならば、公的融資と同じ無利子で借りられます。
大手のプロミスやアイフルなら最短18分以内※で融資が完了し、最大30日間金利が0円に。
くわえて自宅にいながら契約も借入もできるのが消費者金融のメリット。
スマホ1台あれば近所のコンビニやATMでお金を借りることも可能です。
緊急小口資金で借りたいと思っているなら、逆にカードローンの方が楽に利用できるケースも。
融資のスピードや手軽さを求めている人は、合わせて検討してみてください。
あなたにぴったりのカードローンを診断!
あなたにぴったりの
カードローンを診断!
 記事監修者:林裕二
記事監修者:林裕二2018年に2級FP技能士検定に合格後、AFP登録を実施。FPライターとして金融系記事をメインに寄稿するとともに、大手金融サイトで記事監修も開始。ファイナンシャルプランナーとして、読者に対して正しい情報を届けられるよう監修を行う。また、ファイナンシャルプランナーとしての専門知識に加え、ライターとして培ってきた知識を踏まえ、専門性の高い監修を行うことを心掛けている。

 サイトマップ
サイトマップ